
ジャグラーシリーズといえば「GOGO!ランプが光ればボーナス確定」というシンプルなゲーム性で、長年にわたり多くのファンから愛されてきたパチスロ機です。その中で忘れてはならないのが、リール図柄やパネルに登場する個性豊かなキャラクターたち。ピエロをはじめとするファミリーキャラクター、ツノっちやトラっぴといった動物たち、さらにはまろ吉やベコたんのようなユーモラスな仲間まで、それぞれにユニークな役割と存在感を持っています。
これらのキャラクターは、直接的にボーナス抽選を左右するわけではありませんが、ジャグラーの世界観を豊かにし、プレイヤーに親しみや楽しさを与える大切な要素です。単純な遊技機にとどまらず、まるでキャラクターと一緒に遊んでいるような感覚を味わえるのも、ジャグラーが長年支持される理由の一つといえるでしょう。
本記事では、そんなジャグラーに登場するキャラクターたちを一体ずつ取り上げ、その由来や役割、プレイヤーから愛されてきた理由を詳しく解説していきます。これを読めば、あなたもお気に入りのキャラクターが見つかり、ジャグラーをより深く楽しめるようになるはずです。
ピエロ
【1996年 初出:初代ジャグラー】

ジャグラーシリーズにおいて「ピエロ」は最も象徴的な存在の一つです。筐体のデザインや演出の中心に描かれるだけでなく、リール上では小役としても登場し、プレイヤーにとって特別な意味を持っています。
小役としてのピエロは、払い出しが大きい反面、出現頻度は非常に低く設定されています。多くのシリーズで出現率は千分の一程度とされ、1日打っても数回しかお目にかかれないレベルです。そのため、揃ったときの満足感は大きく、プレイヤーに「今日は引けた」というちょっとした達成感を与えてくれます。
しかし実戦上、ピエロを取りにいくかどうかはプレイヤーのスタイルによって分かれます。一般的なチェリー狙いの打ち方をすると、ピエロやベルといったレア小役はどうしても取りこぼすことになります。取りこぼしを避けたいなら逆押しを駆使する必要がありますが、その分だけ目押しの負担や時間効率が落ちるため、ほとんどのプレイヤーは割り切ってチェリーを優先しています。実際、ピエロを完全にフォローしたとしても出玉的な影響はごくわずかで、大きな勝敗を左右するほどではありません。
一方で、ピエロは単なる小役ではなく、ジャグラーという世界観を形作るキャラクターでもあります。シルクハットをかぶった陽気な姿は、ジャグラーを象徴するイメージそのものです。また、このキャラクターから派生した「ジャグリー(女性ピエロ)」「ジャグビー(赤ちゃんピエロ)」「ジャグミー(妹ピエロ)」といった“ピエロ・ファミリー”も存在し、シリーズを彩る要素としてプレイヤーに親しまれています。
つまりピエロは、ゲーム性とブランド性の両面を担う重要な存在です。リール上での役割は限定的でも、その存在感は絶大であり、長年にわたってジャグラーが多くの人に愛され続ける理由の一つになっています。

初代ジャグラーは元々は『ピエロ』という機種名で登場する予定だったようで、このデザインはその名残を感じる。
ジャグビー
【1996年 初出:初代ジャグラー】

ジャグラーシリーズのキャラクター群の中で、特にユニークな存在が「ジャグビー」です。名前のとおり赤ちゃんをモチーフにしたピエロで、見た目はおしゃぶりをくわえた小さな姿が特徴的。ピエロファミリーの中で最も幼い立ち位置にあり、シリーズの世界観を柔らかく、親しみやすく演出する役割を担っています。
ジャグビーはパネルデザインや公式イラストで登場することが多く、筐体の雰囲気を和ませる存在です。ジャグラーといえば「光ったらボーナス!」というシンプルさが魅力ですが、そこにこうしたキャラクターが加わることで、単なる遊技機ではなく“キャラクター性を持ったエンターテインメント”へと進化しています。特にジャグビーのような子どもキャラは、プレイヤーに安心感や親しみを与えるだけでなく、シリーズ全体をファミリー的なイメージで捉えさせる効果があります。
実際の遊技においてジャグビーが直接的な役割を持つことはほとんどありません。リール上に出現するわけでもなく、ボーナス抽選に関わる小役でもないため、実戦的には「背景キャラ」に近い立ち位置です。しかし、プレイヤーの中には「今日はパネルにジャグビーがいる台を打ちたい」と、キャラクターを理由に台を選ぶ人もいます。これは演出面だけでなく、キャラがブランディングの一部として機能していることを示しています。
また、ジャグビーの存在はジャグラーシリーズが長年にわたって幅広い世代に愛されてきた背景の一端でもあります。パチスロは本来、大人が楽しむ遊技ですが、ジャグラーのキャラクターたちはあえてポップで親しみやすいデザインにすることで、嫌な圧迫感を与えず、むしろ「ちょっとかわいい」印象を残します。その中でもジャグビーは、ピエロファミリーにほっとする柔らかさを添える役割を果たしているのです。
まとめると、ジャグビーは実戦面では特別な効果を持たないものの、キャラクターとしての存在感は大きく、ジャグラーシリーズ全体のイメージ作りに貢献しています。ジャグラーが単なるパチスロ機種ではなく、一つの“世界観を持ったブランド”として認知される背景には、このような細やかなキャラクターデザインがあると言えるでしょう。

マイジャグラーシリーズでは片方のチェリーに隠れるような形でも登場している。

ジャンキージャグラーではピエロ絵柄のような形でリール絵柄としても登場しており、近い将来ピエロの後釜を務める事になるのかも知れない。
ジャグリー
【1996年 初出:初代ジャグラー】
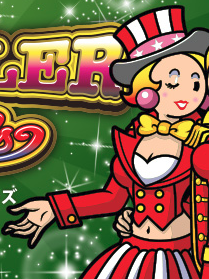
ジャグラーシリーズの世界観を彩るキャラクターの一人が「ジャグリー」です。彼女はシルクハットをかぶった陽気なピエロ「ジャグラー」の仲間であり、女性らしい雰囲気を持ったデザインが特徴です。大きな瞳やリボンなど、可愛らしさを前面に押し出した姿で描かれ、ジャグラーのキャラクター群に華やかさを加えています。
ジャグリーは、ジャグラーのマスコット的な立ち位置を担いつつ、単なる飾りにとどまらない役割を果たしています。歴代シリーズのパネルや演出の一部では、ジャグラーや他の仲間たちとともに登場し、筐体の雰囲気を明るくする存在となっています。彼女がいることで「ただのスロット機械」ではなく、一種のエンターテインメント空間としての個性が強調されているのです。
また、ジャグリーはピエロキャラクターの派生として生まれたことで、プレイヤーに「シリーズの世界が広がっている」という印象を与えています。単にリールの出目やランプの光り方だけで楽しむのではなく、キャラクター同士のつながりや設定を想像させることで、ファンの愛着を深める効果があります。特に長年ジャグラーを打ち続けているプレイヤーにとっては、こうした“家族や仲間の存在”が親しみを感じる要因になっています。
一方で、ジャグリーはゲーム性に直接影響する役割は持っていません。リール上の小役や演出抽選といった部分に関わるのは主にチェリーやピエロといった図柄であり、ジャグリー自身が「何かを引き起こすキャラ」として扱われることはほとんどありません。それでも、彼女の存在はプレイヤーの心を和ませ、ジャグラーというシリーズを「愛されるブランド」に押し上げる力を持っています。
まとめると、ジャグリーはジャグラーの世界における“彩り”のキャラクターです。機械的な部分には関与しなくても、華やかで親しみやすいデザインはプレイヤーに安心感と楽しさを与え、長く愛されるシリーズの魅力を支える要素になっています。
ジャグミー
【2013年 初出:ジャグラーガールズ】
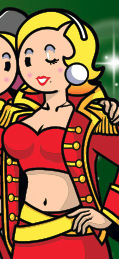
ジャグラーシリーズに登場するキャラクターの中で、少し特別な立ち位置にいるのが「ジャグミー」です。彼女は“ピエロの妹”という設定を持ち、女性らしいかわいらしさを前面に出したデザインで描かれています。リボンや明るい色合いの衣装など、兄であるピエロとは違った柔らかさを持ち、シリーズの世界観に幅を与える存在です。
ジャグミーは実戦に直接関わる役割を持つキャラクターではありません。リール上の小役や抽選に影響を与えることもなく、ゲーム性に直結するのはチェリーやピエロといった定番の図柄です。しかし、彼女の存在はプレイヤーにとって「ただの遊技機を超えた楽しさ」を感じさせてくれます。パネルに登場したり、公式イラストで兄や他の仲間と一緒に描かれることで、シリーズ全体に“ファミリー感”や“親しみやすさ”を付与しているのです。
特に長年ジャグラーを楽しんでいるファンにとって、ジャグミーはキャラクター展開の一環として注目されることが多いです。ピエロがシリーズの顔であり、ジャグリーやジャグビーが世界観を広げている中で、ジャグミーは「妹」という立ち位置から親近感を持たれやすく、可愛らしさの象徴のように扱われています。女性キャラクターの存在は、ジャグラーが単なる機械ではなく、“ブランドとしての個性”を確立するために重要な役割を果たしているといえるでしょう。
また、パチスロはどうしても「ギャンブル」という側面が強調されがちですが、ジャグミーのようなキャラクターがいることで、ジャグラーは明るくポップな印象を強めています。カラフルで可愛らしいデザインは、シンプルなゲーム性と合わさり、幅広いプレイヤー層から受け入れられる理由の一つになっています。
まとめると、ジャグミーは直接的なゲーム性には関わらないものの、シリーズ全体の魅力を支える重要なキャラクターです。彼女の存在があることで、ジャグラーは“遊技機”の枠を超えて“愛されるコンテンツ”へと発展しており、プレイヤーにとっては心を和ませる存在となっています。
ツノっち
【1996年 初出:初代ジャグラー】

「ツノっち」は、ジャグラーシリーズのリプレイ図柄としておなじみのサイのキャラクターです。名前の由来は、そのまま「角(ツノ)」から取られたもので、親しみやすさを込めて“っち”が付けられています。リール上ではリプレイを表す絵柄として長年採用されており、ジャグラーシリーズを支える小役キャラクターの代表格といえます。
ツノっちがプレイヤーにとって印象深いのは、そのデザインと存在感です。シンプルなジャグラーの世界観において、リールの回転中にふと目に入るツノっちの姿は独特の安心感を与えます。ジャグラーは派手な液晶演出を持たず、ランプ点灯とリール出目が最大の見せ場となる機種ですが、その中でツノっちは遊技の“日常風景”を彩るキャラクターとして根付いてきました。
また、リプレイはジャグラーにおいて非常に重要な役割を果たします。リプレイ確率が高いことはコイン持ちの良さにつながり、長時間遊技を楽しむうえで欠かせない要素です。そのリプレイを象徴するのがツノっちであるため、単なる図柄以上に「安心の象徴」として親しまれてきました。
キャラクター展開としても、ツノっちは他の仲間たちと一緒に公式イラストやパネルに登場することがあります。トラっぴ(トラのキャラ)やまろ吉(犬キャラ)と並んで紹介されることもあり、ジャグラーの世界を賑やかにするファミリーの一員として扱われています。
総じてツノっちは、**「リプレイ=ツノっち」**という図式を確立した、ジャグラーを象徴するキャラクターのひとりです。ゲーム性を支える実利的な役割と、長年にわたりプレイヤーに親しまれるビジュアル的な魅力を兼ね備えた存在といえるでしょう。
過去に北電子から登場した「SAIsai」という機種では、めでたく主役を張っていました。
本来はジャグラーのリプレイ絵柄と言えば「ツノっち」というほどの絶大な存在感を示していたが、機種自体の人気でマイジャグラーシリーズに大きく水をあけられており、ジャグラーシリーズにおけるリプレイ絵柄の代名詞としての地位が揺らいでいる。
オっぽ
【2004年 初出:ゴーゴージャグラーV】

ジャグラーシリーズのキャラクターの中でもユニークなのが「オっぽ」です。リスをモチーフとしたキャラクターで、名前は「尾っぽ(しっぽ)」に由来しています。さらに、リプレイを意味する“リスタート”の「リス」と掛け合わせた言葉遊びも含まれており、単なる図柄以上の遊び心が込められています。
リール上ではリプレイ小役を表すキャラクターとして描かれ、しっぽが「R」の形になっているのが特徴です。このデザインは「リプレイ=再スタート」の意味合いをビジュアルで表現しており、ジャグラーらしいシンプルさとユーモアを両立させています。
オっぽが初めて採用されたのはハッピージャグラーシリーズで、5号機以降の一部機種にリプレイ図柄として登場しました。それ以来、パネルや演出の中でも顔を出すことがあり、ファンの目を楽しませています。特に「隠れオっぽ」と呼ばれるプレミアム演出では、普段は意識しない存在が突然現れることで、プレイヤーにサプライズを与えてくれます。
ゲーム性の面では、リプレイはジャグラーにおけるコイン持ちを支える重要な小役です。その象徴としてオっぽが存在することで、単なる記号的な役割を超えて「安心感」と「親しみやすさ」を演出しています。プレイヤーにとっては、オっぽを見るだけで“また次のゲームを楽しめる”というポジティブな気持ちを喚起させるキャラクターといえるでしょう。
まとめると、オっぽはリプレイ図柄に新しい個性を与えた存在です。リスらしい可愛さと語呂遊びのセンスが光り、ジャグラーシリーズのキャラクターラインナップの中でも異彩を放っています。直接的に出玉を左右するキャラではありませんが、遊技体験を豊かにする大切な要素として、ファンに親しまれているキャラクターです。
トラっぴ
【2010年 初出:マイジャグラー】

ジャグラーシリーズに登場する動物キャラクターの中で、特に目立つ存在が「トラっぴ」です。名前の由来は分かりやすく、トラをモチーフにして「トラ」+親しみやすい語尾「っぴ」を組み合わせたもの。可愛らしい語感と、力強い動物のイメージを同時に持たせています。
トラっぴはリプレイ図柄として採用されることが多く、リール上に描かれることでプレイヤーに親しまれてきました。キャラクター自体はシンプルで、元気いっぱいのトラの姿が印象的です。ジャグラーの演出は「光ればボーナス」という明快さに徹している分、こうしたリール図柄のデザインが遊技中のちょっとした楽しさを演出しています。
また、ジャグラーのキャラクター群は、プレイヤーに「世界観の広がり」を感じさせる役割を持っています。ツノっち(サイ)、オっぽ(リス)、まろ吉(犬)などと並び、トラっぴも仲間の一員として紹介されることが多く、ジャグラーを単なる遊技機ではなく“キャラクター性を持つブランド”に押し上げる重要な要素のひとつになっています。
ゲーム性の観点から見ると、リプレイはコイン持ちを支える基本的な小役です。トラっぴはその象徴として登場し、プレイヤーに「また次のゲームへ進める」というリズム感を与える存在といえます。実際には抽選や出玉に直接関与するわけではありませんが、その姿を見ることで安心感を得られるプレイヤーも少なくありません。
まとめると、トラっぴはジャグラーシリーズの“動物キャラクターライン”を代表する存在であり、親しみやすく力強いデザインでプレイヤーを楽しませています。彼の存在によって、ジャグラーはシンプルな遊技性の中にも豊かな世界観を持つシリーズとして愛され続けているのです。
ベコたん
【2011年 初出:ミラクルジャグラー】

「ベコたん」は、ジャグラーシリーズに登場するリプレイキャラクターの一つで、モチーフはウシです。「ベコ」は東北地方の方言で牛を意味し、それに親しみを込めた「たん」をつけた名前になっています。こうした語感の柔らかさが、ジャグラーらしいユーモアと可愛らしさを感じさせます。
ベコたんはリール図柄として登場するほか、シリーズによってはパネルデザインやイラストにも描かれています。コロンとした丸みのあるデザインと愛嬌のある表情が特徴で、動物キャラが多いジャグラーの中でも特に“ほのぼの感”を強く出しているキャラクターです。プレイヤーにとっては、ただのリプレイ図柄ではなく「ちょっとした癒やし」を与えてくれる存在といえるでしょう。
リプレイはジャグラーにおける遊技を支える小役であり、その象徴としてのキャラクターがベコたんです。頻繁に目にするリプレイに可愛いキャラクターを与えることで、長時間の遊技でも飽きにくく、視覚的にも楽しい時間を演出してくれます。また、牛という動物は古来から豊穣や安定を象徴する存在でもあるため、無意識に縁起の良さを感じるプレイヤーもいるかもしれません。
ゲーム性への直接的な影響はありませんが、ベコたんのようなキャラクターがいることで、ジャグラーシリーズは単なる「光ったら当たり」の機械以上のものになっています。キャラクターが世界観を作り、プレイヤーに愛着を持たせることで、長年にわたり支持を集めるブランドへと成長したのです。
まとめると、ベコたんは「牛=ベコ」をモチーフにした親しみやすいリプレイキャラクターで、愛嬌あるデザインと名前でファンに愛されています。実戦的な役割は小さいものの、ジャグラーを単なる遊技機ではなく“キャラクターと楽しむコンテンツ”に押し上げる存在のひとつといえるでしょう。
チュー助
【2013年 初出:みんなのジャグラー】

ジャグラーシリーズに登場するキャラクターのひとりに「チュー助」がいます。名前の通り、モチーフはネズミで、リプレイ図柄として採用されている動物キャラの一員です。「チュー」という鳴き声と、親しみやすい「助」を組み合わせたネーミングは、シンプルで覚えやすく、多くのプレイヤーに浸透しています。
チュー助は、ツノっち(サイ)、トラっぴ(トラ)、オっぽ(リス)、まろ吉(犬)と並ぶ“リプレイキャラクターライン”の一つを担っており、ジャグラーの世界を賑やかに彩っています。リール上に出ると「コインが減らない」「次ゲームに進める」という安心感をプレイヤーに与えるのがリプレイの役割であり、その象徴としてチュー助が存在しています。
また、ネズミという動物は小さくてすばしっこいイメージがあり、パチスロにおける軽快なゲームテンポともよく合っています。キャラクターデザインも可愛らしく、明るいジャグラーの世界観にマッチしています。ジャグラーシリーズは派手な液晶演出を持たない分、こうしたリール図柄のデザインやキャラクター性がプレイヤーの気持ちを和ませ、長時間の遊技でも飽きさせない工夫になっているのです。
ゲーム性に直接影響を与えるキャラではありませんが、チュー助をはじめとしたリプレイキャラクターたちは、単なる小役図柄を超えて「親しみやすい仲間」としてプレイヤーに印象を残します。こうした細かなキャラクター展開が、ジャグラーシリーズが長年愛されてきた理由の一つだといえるでしょう。
まとめると、チュー助はリプレイ小役を象徴するネズミキャラクターであり、親しみやすいネーミングと可愛らしいデザインでプレイヤーに愛される存在です。ゲーム性の中心には関わらなくても、シリーズ全体の世界観を支える大切なキャラクターといえます。
まろ吉
【2016年 初出:ファンキージャグラー】
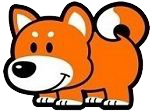
ジャグラーシリーズのキャラクターの中でも特にユーモラスなのが「まろ吉」です。モチーフは犬で、ファンキージャグラーシリーズのリプレイ図柄として登場しました。見た目は愛嬌たっぷりの犬で、「ワンモア!」=リプレイ成立を犬の鳴き声「ワン」と掛け合わせた発想から誕生したキャラクターです。名前の「まろ吉」も、公式に行われた公募で決定したもので、多くのプレイヤーから親しまれています。
リプレイ図柄はジャグラーにとって遊技を支える大切な役割を担っており、その象徴としてキャラクターを用いることで、単なる記号的存在から「遊び心のある仲間」へと昇華しています。まろ吉はその代表例といえるでしょう。特にファンキージャグラーでは、従来のシンプルなピエロや動物キャラに加え、こうしたユーモラスなキャラクターを採用することで、プレイヤーに新鮮さと親しみを与えています。
演出面では、まろ吉が表に出ることで「今日は犬の台を打ちたい」とキャラクターを理由に台を選ぶ人も出るほどです。直接抽選に影響することはありませんが、遊技のモチベーションや楽しさを高める効果は大きいといえます。さらに、「リプレイ=もう一度挑戦できる」という前向きな意味合いを持たせている点も、長時間遊ぶプレイヤーにとってポジティブに働いています。
まとめると、まろ吉はファンキージャグラーから加わった“新世代のリプレイキャラクター”であり、親しみやすさと遊び心を兼ね備えた存在です。キャラクターの可愛らしさに加え、名前がプレイヤー参加型で決められた背景も含めて、ファンに深く愛される理由となっています。
ゾウ
【2004年 初出:ゴーゴージャグラー】

ゴーゴージャグラーシリーズで目を引く「ゾウ」のキャラクターは、リール図柄や演出とは直接的には関わらず、主にパネルや広告ビジュアルとして登場する“シンボル的存在”です。明るい色彩とかわいらしいデザインは、ジャグラーシリーズのシンプルなゲーム性に華やかさを添えており、プレイヤーの目を引きつける重要な役割を担っています。
現時点では、ツノっちやトラっぴなどのように公式名称があるわけではなく、明確な名前や由来は確認されていません。そのため、ゾウは“キャラクター性”というより“デザイン的演出”として位置づけられていると見るのが自然です。
視覚的魅力と親しみやすさを高める効果を持ちながら、正式なキャラクター設定は付されていない――。このような曖昧さも含めて、ゴーゴージャグラーらしい“ポップかつミステリアスな存在”と言えるかもしれません。
©KITAC
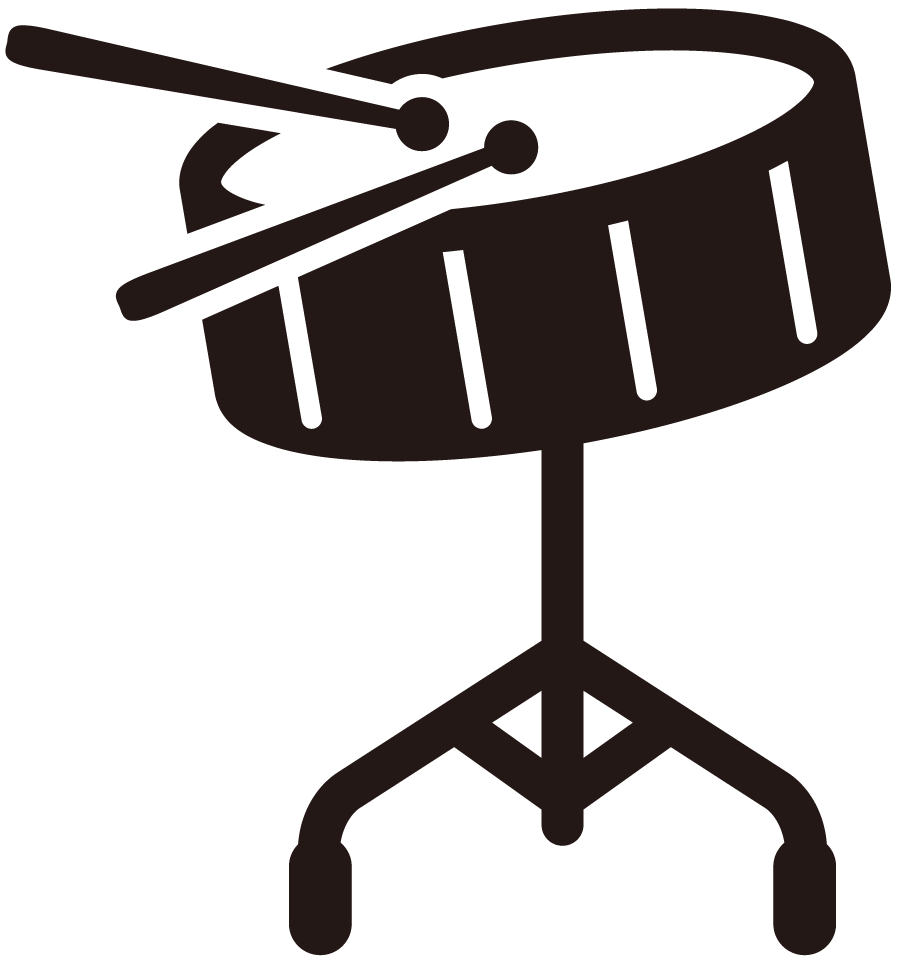 ジャグジャグBeats!
ジャグジャグBeats! 
